![]()
![]()
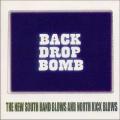 |
BACK DROP BOMB |
BACK DROP BOMBのインディーズ盤。96年の作品。当時、メロコアやスカコア的なバンドばかり聴いてた僕はこの作品を聴いて衝撃を受けた。ロックにヒップホップの要素(逆かも)、そしてラガも。グルービーなバンド・サウンドに絶妙の英語2MC。そこに加わるサックスもいい味出している。DJ
HASEBEをフィーチャリングした完全にヒップホップな曲なんかもあって全体的に質が高い。『MICROMAXIMUM』を聴いた今では、ちょっと物足りないけど今、聴いても十分かっこいい作品だと思う。 今でこそ、日本でもヒップホップ×ロックみたいな所謂ミクスチャー・ロックは普通になってきているけど96年にこの作品を作ったBACK DROP BOMBは本当に凄いな。BACK DROP BOMB以後、多くのフォロワー・バンドが現れたけど、この作品すら越えてないバンドがほとんどだ。 そして、僕はこの作品を知ってからレイジなどの外国のミクスチャー・バンドを聴いたんだけど、BACK DROP BOMBはそれらのバンドと比べても決して劣らないと思う。日本最強のミクスチャー・バンド。 |
 |
BACK DROP BOMB 『MICROMAXIMUM』 |
日本のミクスチャーの大御所BDBの1stフルアルバム。メジャーのレコード会社からリリース。DJ
WATARAIのヒップホップ・トラックで幕を開けるこのアルバムはハードコア、ヒップホップ、レゲエ、スカ、ボサノバなどをBDB流に自然な形で融合させた、これぞミクスチャーという作品。格段にセンスが良く他の猿真似バンドとは比にならない出来です。 |
 |
BACK DROP BOMB |
BACK DROP BOMBのリミックス盤。 |
 |
BACK DROP BOMB 『NIPSONG』 |
バック・ドロップ・ボムの前作から約3年ぶりとなる2ndアルバム。前作に比べると、サックスの入った曲もなくなって、陽気さも減少、かなりシリアスな内容。最初、パッと聴いた印象は、サウンドの幅が狭くなって面白くないな・・・って感じだったけど、何回か聴くうちにどんどんハマっていった。 力強いツイン・ボーカル、PELEやTOEなどのポストロックや、ダブなんかも通過した高度な演奏。そして、アレンジが秀逸。パッと聴きでは分からなかったけど、1曲の中に、これでもかってくらいのアイデアが盛り込まれている。こんな演奏には、こんな歌メロとか、AメロがあってBメロ、そしてサビとかいう、常識から逸脱したアレンジ。転調に次ぐ転調。とにかく変態的。それなのに、ちゃんとノれる音楽になっているところが凄い。 もうホント最高なの。邦楽か洋楽、ロックかミクスチャー・・・そんなこと関係なしにカッコいい。DJ WATARAIが作ったイントロ、アウトロを含めて最初から最後まで全部カッコいい。ロック好きな人は是非是非。ヘヴィロックやミクスチャーなんて・・・とか日本のロックなんて・・・って人も聴いてみるといいと思うよ。今年に聴いたロック作品の中でもトップクラスの出来。メチャクチャお薦めです。 あと、初回盤にはライブ・トラックを3曲収録したディスクが付いてるんで、お早めに。 |
 |
BACK DROP BOMB 『DIVERSIVE AUDIO EP』 |
こりゃ参った。なんかの記事でポストパンクやエレクトロクラッシュの要素をどうたらって書いてあるのを見て、嫌な予感がしてたんだけど良い意味で裏切られた。たしかに流行ぎみなラプチャーを始めとするポストパンク・リバイバル的サウンドの要素は盛り込まれてるんだけど、ただ猿真似するんじゃなくて『NIPSONG』以降のバック・ドロップ・ボム(BDB)独自のサウンドに巧くポストパンクやエレクトロクラッシュを取り入れた感じ。これはポストパンク・リバイバルというより、ポストパンク・エボリューションだね。 とにかくM-1『IN ORDER TO FIND THE NEW SENSE』が凄い。BDBらしく転調に次ぐ転調、何曲分のアイデアや様々なジャンルの要素が一曲の中に、しかもポップに同居。聴けば聴くほど新しい発見があってズボズボはまっていく中毒性の高さ。バンドサウンドと打ち込みの融合やメロディーもホント絶妙。正直、ラプチャーなんかよりもずっとかっこいいと僕は思うよ。その手の音が好きな人は騙されたと思って聴いてみて欲しいな。名曲。 M-2『THE AIR』はBDBにしては珍しくストレートに疾走するパンキッシュでヘヴィでポップなロック・ナンバー。サビでの高揚感が半端ない。M-3『UNFAMILAR SIGHT』とM-4『GETTIN' IT ON』は打ち込みを大幅に導入したエレクトロ・ナンバー。後者は『NIPSONG』の『OUTRO』をリコントラクト。ほぼ全編打ち込みサウンドになってるんで、初期からのファンは戸惑うかもしれないけど、どちらもロックバンドやってたけど流行に乗ってエレクトロやってみました感は全然なくて、完成度が高く渋い出来上がりになっている。 そしてM-5『NEVASHINEDD』は『NIPSONG』収録の『NEVERSHINED』をメンバがメロウなハウスにセルフ・リミックスしたものなんだけど、もうメチャクチャかっこいいの。この曲と名曲すぎるM-1だけのために買っても定価の1500円は安すぎだと思うよ。今のBDBはアウトキャストやN.E.R.D.、!!!(CHK CHK CHK)なんかに通じるところがあると思うんだけど、それらのアーティストと並べても見劣りしないね。傑作。 |
 |
B-DASH 『B-DASH BEST』 |
ごめんなさい。僕は今までB-DASHのことを聴かず嫌いしてました。でも、このベスト盤で初めてちゃんと聴いてみてB-DASHが好きになったよ。B-DASHには何となくありがちなメロコア&青春パンクなイメージを持ってたんだけど全然そんなことないね。確かに中にはブルーハーツ直系というかBAKU直系というか、そんな感じの曲もあるんだけど、例えば2曲目の『ちょ』で見せてる「おーううぇーあーれ そー円ちゅーあん
Mo ーい」「医療隊マッカラ号 立派な拳法界
正方位 」なんていう意味不明な歌詞や6曲目『人造ライダーイマーン』で見せてる架空のアニメソングみたいなユーモラスな歌詞、そして4曲目の『SECTER』や13曲目の『目覚めよニッポン!』なんかで見せてる転調しまくりな曲展開などなどB-DASHならではの魅力がいっぱい。 何も考えずにメロディや曲展開を楽しめる意味不明の歌詞や単純に楽しいヘンテコな歌詞が一回聴いただけで口づさめるような激ポップ・メロディと一体になってスピード感いっぱいに転調しまくり。いやあ、楽しいなあ。やっぱり聴かず嫌いは良くないね。いい曲ばかり22曲収録で2000円とお買い得だけどCCCDなのが玉にキズ。 |
 |
B-DASH 『ホフ』 |
B-DASHの7曲入りミニアルバム。ブルーハーツ直系なビートパンクから、お得意の転調しまくりポップパンク、日本語スカコア、ミディアムなテンポでしっかりメロディと言葉を聴かせる歌物ナンバー、妙にポップなスラッシュコアなどなどバラエティに富んだ7曲になってます。どんな曲をやってもB-DASHらしさみたいなものが感じられて、いいバンドになってきたなって印象です。 今作はまともな日本語の曲が多くて、B-DASHのウリのひとつだった意味不明な日本語を期待してた人は残念に思うかもしれないけど、あれはある意味、逃げだったと思うんだよね。このギミックがあったから、ここまで来れたし、もちろんB-DASHの個性だったし、個人的にも面白かったけど、もう音楽の本質だけでB-DASHらしさを出せるようになったんだから、変にギミックに頼らなくてもいいと思う。完全にやめちゃうのは寂しいけど、もうそれを前面に出す必要はないんじゃないかな。 |
 |
BADLY DRAWN BOY |
映画『ABOUT A BOY』のサントラなんだけど、実質的にはバッドリー・ドローン・ボーイ(BDB)が全編を手掛けていて、BDBのアルバムと言ってもいい内容。 |
 |
BAGDAD CAFE THE trench town |
関西の11人編成ビッグバンド、BAGDAD CAFE THE
trench townの1stアルバム。 よく横浜が日本のレゲエの聖地みたいに言われることがあるけど、あの辺の横浜レゲエ祭に参加してる系のアーティストに比べて大阪のほうが遥かに優れたレゲエ・アーティストが多い気がするのは僕だけかな?このBAGDAD CAFE THE trench townも本当に素敵なレゲエ、ラヴァーズ・ロックを聴かせてくれる。陽気なホーンセクションをフィーチャーしたレゲエ・サウンドに、MAYのソウルフルな日本語ボーカル。それを彩る温かいコーラス。暖かく優しく心地よい至福のサウンド。僕はこのアルバムを聴くと思わず笑顔になってしまう。ラヴァーズ好きな人は是非是非。EGO-WRAPPIN'あたりを好きな人も是非是非。あと三木道三を聴いて大阪のレゲエに変な偏見を持っちゃった人も是非是非。日本のレゲエも捨てたもんじゃない。次はインスト曲もちょっと聴いてみたいな。 |
 |
BAGDAD CAFE THE trench town 『UP RIGHT AND SMILEY』 |
大阪のレゲ・バンド、バグダッド・カフェ・トレンチ・タウンのセカンド・アルバム。開放感溢れるレゲエ・ビートとソウルフルなホーンセクション、そこに絡まるボーカルMAIの伸びやかで艶やかな歌声とRANとBIG
MAMAの心地よいコーラスワーク、最高にハッピーなラヴァーズ・サウンドを聴かせてくれます。もう心地よすぎ。タイトル通り、笑顔になれます。どんなに暑くて汗ダラダラ食欲ゼロな日でもこれがあれば幸せに過ごせるよ。 この人たちの曲はサウンドが心地よいのはもちろん、歌とメロディーが立ってるのが素敵だね。「レゲエってなに?ジャマイカなんて知らない」っていうような人も全然巻き込める力があると思う。実際、この人たちの曲は関西のFM曲でヘヴィーローテーションにもなってたしね。全8曲で捨て曲なし。ラヴァーズ・レゲエ好きな人はもちろん、いっぱい笑顔になりたいレゲエ初心者の人にもお薦めです。 |
 |
BAMBI SYNAPSE 『WEATHER FORECAST』 |
CONVEX LEVELの渡辺良、その奥さんの渡辺美智代、TANZMUSIKの佐脇興英(オキヒデ)の3人組、BAMBI
SYNAPSEの1stアルバム。 浮遊感のある美しいトラックに生ドラム、そして、透き通った美しい女性ボーカル。クラリネットの音もいい。全編通してキラキラしてて、恍惚感がたまらない。ただただ気持いい音。全曲いい感じです。特に、エレクトロニクス×生ドラム×女性ボーカルにバイオリンまで加わった、M-6『TRAUM』は名曲。96年の作品だけど古臭くなく、今聴いても新鮮な作品です。 |
 |
BAMBI SYNAPSE 『LIFE』 |
BAMBI SYNAPSEの2ndアルバム。 渡辺美智代による澄んだ女性ボーカルと美しいクラリネット、渡辺良のタイトなドラム、佐脇の浮遊感のあるシンセ、そしてノイズが融合した美しい電子ポップ。浮遊感のあるふわふわした曲から、激しいビートの曲まで、どれもカッコいい。 98年にリリースされた作品だけど、現在のエレクトロニカ・シーンにも通づるような作品。なかなかの出来だけど個人的には前作のほうがキラキラ感があって好きかな。 |
 |
BANANA BOAT 『WHAT'S THE THING WE DO FIRST?』 |
POTSHOTのボーカルRYOJIが主宰するTV FREAK
RECORDSから98年にリリースされたバナナボートの唯一のフルアルバム。このアルバムが出た頃は日本のインディー・シーンはメロコア・ブーム。僕もその時期は思い切りメロコアにはまっててメロコアのCDを片っ端から買いあさってた。ハイスタやシャーベット、ニコチン、ゴエモン、ドーナツマン、グーフィーズホリデイ、スプレッド、ミスターオレンジ、ソバット、ショートサーキット・・・好きなバンドや作品もいっぱいあったんだけど、その中でも最も好きだったのが、このアルバム。 サウンドはジャケットの絵みたいにビーチが似合いそうな陽気なメロコア。当時、ハイスタにそっくりだとかよく言われてたけど、メロディーラインやコーラスワーク、ギターリフなど、たしかに似てる部分は多い。でも一番共通しているのは最高のメロコアだっていう部分。歌、演奏、アレンジ、メロディー、ドライブ感、どれをとってもホント最高だよ。全曲最高。ハイスタを好きな人、メロコアは好きだけど聴いたことないって人は騙されたと思って聴いてみて。傑作中の傑作だよ。というか名盤。この1枚のみで解散してしまったのがホントに惜しい。 |
 |
BANDWAGON 『THE EQUIPMENT!!!』 |
フルアルバムを出さずに解散してしまたっんだけど、OATMEALっていうパンクバンドがあった。強烈なツインギターとエモーショナルなボーカル、そして複雑な曲展開。決してわかり易くはないんだけど非常に中毒性の高いサウンドで、たった4曲しか入ってないEPを僕は死ぬほど聴きまくった。本当にいいバンドだったんだけど残念ながら解散。後にそのOATMEALのメンバー、ナベカワミツヨシとアキモトタカジが中心となって結成された新しいバンドがBANDWAGON。これはBEAT
CRUSADERSと同じレーベルよりリリースされた記念すべき彼らの1stフルアルバム。 もうこれがOATMEALが持っていた静と動のコントラスト、美メロ、ツインギターによる重厚なサウンド、複雑な曲展開などにより磨きをかけた大傑作。知的でありながら非常にダイナミック、エモやポストロックを軽く通り越した高度な演奏に、時には美しく時には激しく、心を揺さぶるようなナベカワミツヨシのボーカル。思わず泣きそうになってしまうな美しいメロディ。それらが複雑にドラマチックに展開する。そして、曲によっては打ち込みやアコーディオン、バイオリンを導入したような曲もあって実験性も忘れちゃいない。アルバム全体の流れも本当にドラマチックで、聴けば聴くほどに魅力の増す非常に奥深い作品になっています。これは名盤と言ってもいいんじゃないかな。 同レーベルのBEAT CRUSADERSみたいにキャッチーではないしテンポの速い曲もないしけど、中毒性は半端ないです。ポストロック寄りのエモ好きな人は是非是非。BACK DROP BOMBを好きな人やTHE BAND APARTを好きな人、あとはくるりを好きな人なんかも是非、聴いてみて欲しいな。大注目のバンドです。 |
 |
BANDWAGON 『NEW MUSIC MACHINE EXTENDED PLAY』 |
バンドワゴンの2作目。ポストロックもエモコアもダブもニューウェーブも柔軟に飲み込んだ唯一無二のロックサウンド。前作もメチャクチャかっこ良かったんだけど、今作はそれ以上にかっこいいです。メロディも曲展開も複雑でアレンジも変態的なのに何なのこの高揚感!ヤバいくらいにエモーショナル!最高にダンサブル!思わず体が動く動く!特別キャッチーとは言えないメロディが不思議とクセになる!クラッシュの名曲『ロック・ザ・カスバ』のカバーも原曲のパワーに全然負けてません。なんかベタ褒めだけど、かっこいいんだから仕方ないね。 ポストロック、エモって呼ばれてる音楽が好きな人にはホントお薦めです。エモって言ってもメロコア経由の泣きメロを叫んでるだけのバンドやギターポップっぽいのを期待すると駄目かもしれないけどね。イギリスのミュージックなんかが好きな人も聴いて欲しい作品。日本のバンドも捨てたもんじゃないでしょ?バックドロップボム好きな人も是非是非。 |
 |
BARAKI 『LOVE CONNECTION』 |
RISE FROM THE DEADのベーシスト、YOUNG-BOがBARAKI名義で発表したアルバム。BOREDOMSのYOSHIMIも参加。 |
 |
BASEMENT JAXX 『REMEDY』 |
サルサ、ラテンなどを強烈なファンクネスでくくった黒いハウス・サウンド。これを初めて聴いたときの衝撃は凄かった。今、聴いてもその衝撃は薄れてない。 『RENDEZ-VU』、『YO-YO』、『JUMP N' SHOUT』、『RED ALERT』、『BINGO BANGO』など当時クラブでもかかりまくってた踊りまくれる曲を多数収録。シングル的な曲を集めたんじゃなくて後半にはしっとりした曲なんかもあって、きちんとアルバムらしくなってるのもいい。 |
 |
BASEMENT JAXX 『ROOTY』 |
BASEMENT JAXXの2ndアルバム。今作はラテン度は薄まって、80年代のディスコ・テイストのハウス・サウンドに。全体的に歌が大幅にフィーチャーされていてキャッチーな印象。キャッチーなんだけど、音作りが凄く凝っている。これは良質のハウス・ポップ。 M-1『ROMEO』は今作の路線を象徴した名曲。キャッチーかつアッパーでダンサブル。最高です。他にも良曲が多くて、大傑作です。パーティーパーティー。前作も良かったけど今作は前作以上。ほぼ同時期に出たダフトパンクの作品よりも僕は断然こっちのほうが好きだ。間口も広いんで、初めてハウスを聴くって人にもオススメ。 |
 |
BASEMENT JAXX 『KISH KASH』 |
BASEMENT JAXXの3rdアルバム。今作は前々作のラテン・ハウスでも、前作の80年代ディスコ・テイストのハウスでもない音。ヒップホップ、R&Bの要素が強めで、UKガラージ、ファンク、レイヴ、ロック、そしてトラディショナルな音楽まで飲み込んだ雑多性の強いダンス・ミュージック。今作はゲスト・ボーカルも、何人かは知らない人がいたけど、UK注目のMC、DIZZEE
RASCAL、M.NDEGOCELLO、そしてインシンクのJC
CHASEZや驚きのスージースーまで多彩な人選。 黒人女性ボーカリスト、LISA KEKAULAのソウルフルな歌をフィーチャーしたアッパーなハウス・チューンM-1『GOOD LUCK』がとにかくメチャクチャ良い。他にもDIZZEE RASCALのMCをフィーチャーしたインド風ガラージ・チューンM-4『LUCKY STAR』、COTLYN JACKSONのボーカルをフィーチャーした最高に黒いファンク・チューンM-6『SUPERSONIC』、インシンクJCをフィーチャーしたM-7『PLUG IT IN』なんかもカッコよかった。そしてスージースーをフィーチャーした問題作M-10『CISH CASH』もアッパーなレイヴ・パンクで最高にカッコよかった。またBASEMENT JAXXのFELIX LARHER自身がボーカルをとり、ストリングスもフィーチャーしたロマンチックなデトロイト・テクノ・チューンM-9『IF I EVER RECOVER』も意外と良かった。前作までとは少し音が違うんで好き嫌いは分かれるかもしれないけど、これはこれで傑作のダンス・アルバムだと思う。 |
 |
BATTLES 『TRAS EP』 |
ブルックリン発の4人組インストバンド、バトルズの1枚目のシングル。3枚目を先に聴いたんだけど、これもかっこいいです。2曲収録で1曲はバトルズらしいナンバーで、グルーヴィーなドラムに、やはりテクニカルに徐々に表情を変えていくギター。踊ってよし聴き込んでよしのナンバーになっています。もう1曲は人力ミニマルテクノ。後者はとっつきにくいかもしれないけど、中毒性があって病みつきになります。 曲自体はどっちも満足。ただ、2曲だけじゃ物足りないよ!もっと曲を!早くフルアルバムを!! |
 |
BATTLES 『EP C』 |
バトルズの2枚目のシングル。凶暴なんだけど、ちゃんとグルーヴ感を作ってるテクニカルなドラムに複雑に変幻自在に絡み合うギター、そしてエレクトロニカ以降の絶妙な電子音。 ニューウェーブ、ポストパンク、プログレ、ジャズ、色んな音楽からの影響は感じられるんだけど、間違いなくバトルズだけの音世界。既存の音の次を行く音世界です。「ポストロック」っていう言葉があって、世間ではよくトータスっぽい感じのインストのことをそう呼ぶみたいだけど、これは本当の意味でポストロックかもね。ただのトータスの真似事じゃ、全然ポストじゃないもんね。とりあえず、色んなジャンルを聴いてて、インストが好きで、刺激のある音を求めてる人は聴いてみてくださいな。個人的にはシングル3部作の中で今作が一番お薦めです。 |
 |
BATTLES 『B EP』 |
ブルックリン発の4人組インストバンド、バトルズの通産3枚目のシングル。テクニカルかつ凶暴に乱れ飛ぶ硬質ドラムと空間をザックザック切り裂くギターサウンド、そこに奇妙な電子音が飛び交い独特の音世界を構築しています。ポップグループやPILみたい80年代ニューウェーブ〜ポストパンクを経由したポストロックって感じかな。EPとはいえ全47分、重く攻撃的なナンバーから疾走するギターインスト、ダブ、アブストラクト、そして高速ドラムが炸裂するハードコア・ダンストラックまでバラエティに富んでます。 いやはやカッコ良い!ただ凶暴なだけじゃなくて、ちゃんと踊れるになってて、音の配置や鳴り方、曲展開が計算され尽くしてる感がとっても素敵です。こりゃアルバムが楽しみだ。ポストロックもプログレもハードコアもニューウェーブも大好きっていう人は、日本の女の子3人組、“にせんねんもんだい”と合わせて聴くと良いかと。 |
 |
bayaka |
DJとしても活躍するMITSURUとTERUOによるユニット。 |
 |
BBQ CHICKENS 『INDIE ROCK STRIKES BACK』 |
活動休止中のハイスタの横山健が率いるハードコア・パンク・バンド。 このBBQ CHICKENにハイスタを期待しちゃいけない。メンバー4人中2人は素人。19曲で18分。カフェオレあり、ビックマックあり、くまのプーさんありの、アンディ・フグあり・・・荒削りで暴走暴走バカバカなハードコア・パンク。時折、横山健らしい美しいメロディラインも顔を覗かすけど、ハイスタより断然ハードコア。とにかく速い速い。勢い一発。バカを楽しめる人向け。 |
 |
BBQ CHICKENS 『GOOD BYE TO YOUR PUNK ROCK』 |
BBQ CHICKENSの2ndアルバムは今作も20曲で20分未満。 前作には少しだけあったキャッチーさも今作にはない。この作品には詳しい説明なんて必要ないと思う。とにかくハードでファストでヘビー、そしてバカ。それだけで十分。 |
 |
BBQ CHICKENS 『FINE SONGS , PLAYING SUCKS』 |
BBQ CHICKENSの3rdアルバムは全曲カバー。カバーしてる曲はブラックサバスの『SYMPTON
OF UNIVERSE』、シャム69の『IF THE KIDS
ARE
UNITED』、バックストリートボーイズの『I
WANT
IT THAT WAY』、『セサミストリートのテーマ』、ビートルズの『DAY
TRIPPER』、マドンナの『LIKE A VIRGIN』、ダフトパンクの『ONE
MORE TIME』、ウィーザーの『GETCHOO』、ニルヴァーナ『TERRITORIAL
PISSINGS』、ボブ・マーリー『BUFFALO
SOLDIER』などなど大ネタ満載。これらの名曲たちを15曲13分で演奏。今作も前作まで同様、いや、それ以上のバカっぷりで突っ走る。 シャム69の『IF THE KIDS ARE UNITED』みたいな違和感ゼロのカバーも普通にかっこよかったけど、今作は意外性満天のビートルズやマドンナのバカバカ・カバーが楽しい。ダフトパンクの『ONE MORE TIME』の絶叫高速ハードコアには思わず爆笑してしまった。このダフトパンクのカバーを笑える人にはメチャクチャ楽しめる作品だと思う。逆に、このカバーはこういうアレンジで〜とか、原曲のメロディを〜とか、リズムが〜とか難しく考えちゃう人には楽しめない作品。頭をカラにして楽しみたい作品。おバカさん推奨。 |
 |
BEASTIE BOYS 『TO THE 5 BOROUGHS』 |
ビースティーボーイズ、スタジオ・アルバムとしては98年の『HELLO
NASTY』から6年ぶりとなる6作目。国内盤はCCCDです。US盤のみ普通のCD。訳詞は見れてないけどブッシュ政権を皮肉ってたり、結構シリアスな内容のリリックも多いみたいです。 音的にもシリアスとはまではいかないけど、これまでほどの破天荒さはない感じ。以前のようなバンド色はほとんど皆無で完全なヒップホップ作品になってます。ジャケットにもニューヨークが描かれてるけど音のほうもモロにニューヨークって感じのオールド・スクール・ヒップホップ。現代的なエレクトロ色も加わってるけど、あまり新しい音ではないかな。とにかく全編に渡って重低音効きまくり。大音量で聴いたらズンズン響いてきて気持ちよすぎ。M-1『CH CHECK IT OUT』やM-6『TRIPLE TROUBLE』あたりのパーティー・チューンが最高。 全15曲で40分ちょっとというコンパクトな作品でサクサク聴けるんだけど、遊び心や飛び道具が少なくてちょっと中だるみするような。もっと遊んでも良かったと思うんだけどなあ。『HELLO NASTY』を聴いた後に聴くと凄く地味に感じる。個人的にはもうちょっとヤンチャで破天荒な音が欲しかったかな。まあ、彼らも結構いい年だし大人になったってことで。 |
 |
BEAT CRUSADERS |
元PESELA-QUESELA-IN のヒダカを中心に結成されたバンド、BEAT
CRUSADERSの1枚目。 |
 |
BEAT CRUSADERS |
BEAT CRUSADERSの2nd。泣きメロ・パワーポップ。前作より少しハードになった印象。 |
 |
BEAT CRUSADERS |
BEAT CRUSADERSのカバー・アルバム。ザ・ポーグス、キャブ・キャロウェイ、ビークルの全身バンドのペセラケセライン、有頂天、堀内孝雄!!!と1stに収録の『E.C.D.T』のセルフカバーを収録。 |
 |
BEAT CRUSADERS 『FORESIGHTS』 |
BEAT CRUSADERSの4枚目。相変わらず、全10曲で約20分。とびっきりのポップさで突き抜けています。 |
 |
BEAT CRUSADERS |
覆面パワーポップバンドBEAT CRUSADERSの4枚目。 |
 |
BEAT CRUSADERS & SKAYMATE'S 『OZZY!!』 |
BEAT CRUSADERSと、モンゴル800のギマタカシ率いる女子6人・男子3人のスカ・バンド、SKAYMATE'Sのスプリット盤。 BEAT CRUSADERSの80年代ニューウェイヴ・パンク的なサウンドと、SKAYMATE'Sのオーセンティック度高めで楽しいスカ・サウンドが見事に融合して、楽しい楽しい。M-1『BABYFACE』は、2組の共演。BEAT CRUSADERSらしいムーグ音とヒダカのポップなボーカル、キャッチーなパンク・サウンドに、SKAYMATE'Sの軽快なホーン、沖縄のバンドってことで、ウチナーグチのコーラスも織り交ざって最高にハッピーなポップ・チューン。1+1が20くらいになってる感じ。かっこいいです。M-2『PARTY NIGHT BOOGIE-WOOGIE』も2組共演。日本語詩でミディアム・テンポのスカ・ポップ。途中にナックの『マイ・シャローナ』のフレーズなんかも飛び出したり、遊び心も満天で楽しい。M-3『BELINDA』は、BEAT CRUSADERS単体の曲。チープでストレートなロックンロール。M-4『バイバイバイキング』は、SKAYMATE'Sの単体の曲。オーセンティック度高めのまったりチューン。この作品の中で、2組のそれぞれの単体曲を聴くとコラボした曲のほうがいいなって思う。ってことは、このスプリット盤は成功だな。M-5『13RONDO』は2組の共演した曲。今度はなんと日本語ジプシー調ロック。映画『黒猫・白猫』の音楽を担当してたEMIR KUSTURICA & THE NO SMOKING ORCHESTRAを思い出した。M-6『ROCK導入』も、2組の共演した曲。渋いスカから始まって、途中からBEAT CRUSADERSらしいキャッチーなギターロックに展開する曲。後半のメロディが凄く良い。M-7『出鱈目同志的賛歌〜校歌編〜』は、お遊びな校歌っぽい曲。たった7曲だけど凄く濃い内容の作品。 |
 |
BEAT CRUSADERS 『BEST CRUSADERS』 |
ボーカルHIDAKA以外のメンバーが全員脱退してしまったBEAT
CRUSADERSのベスト・アルバム。なんと28曲も収録。アルバム収録曲から、今では手に入らない貴重な音源、ライブ音源、未発表曲『BIG
TIME』も収録。最初から最後までベスト。こうやって改めて、このベストを聴くと本当に良曲揃いなことに気付く。このバンドはとにかくメロディ・センス抜群。そして遊び心いっぱいのアレンジ。たまらなく良い。 日本にWEEZERチルドレンなバンドは数あれど、その中でビークルは頭3つくらい抜けてると思う。少なくとも僕が知ってる、そういうバンドの中ではNO1。WEEZERの1stは泣きのメロディとエモーショナルなサウンドばかりが注目されがちだけど、それでいて遊び心もタップリなところが名盤たる所以だと思う。ビークルはこの遊び心の点もバッチリ。むしろ本家よりも上かもしれない。メロディも本家と同様、いや、それ以上のレベルだと思う。 このベスト・アルバムはWEEZERやメロディアスなパンク、ギターポップを好きな人は買っても後悔しないと思う。CCCDっていう点を除いては・・・。あと欲を言えば、ビークルってコンピに収録されたカバーの名曲がいっぱいあるんだけど、それも収録して欲しかったな。でもまあ、アルバム一枚分くらいは十分にあると思うから、コンピ収録曲を集めたアルバムもリリースして欲しい。契約問題が難しいだろうけど。 |
 |
BEAT CRUSADERS 『GIRL FRIDAY』 |
思ったよりもカナリ早めの復活シングル。新生ビークルのメンバーはボーカルはもちろん、ヒダカトオル(Vo)、ギターにGALLOWのカトウタロウ、ベースに元POPCATCHERのクボタマサヒコ、ドラムにNATSUMENのマシータ、そしてキーボードにMONG
HANGのケイタイモという布陣。POPCATCHERは大好きだったし、NATSUMENもMONG
HANGも好きだし僕にとっちゃ豪華メンバーだ。いままでのファンとかは寂しいって気持ちもあって賛否両論あるだろうけど、過去は過去。これはこれで僕は良いと思う。サウンドの方はNATSUMENとかMONG
HANGとかはプログレっぽいし、ちょっとサウンドも変わるかなって思ってたけど、それほど変化したって印象はなかった。変わったと言えば、演奏力くらいかな。遊び心や良質メロディなどのビークルらしさは残しつつタフになった感じ。ビークルの特徴のひとつでもあったヘッポコ感はだいぶ影を薄めてしまった。でも、この3曲を聴く限り、それがマイナスだとは思わなかったな。人それぞれだと思うけど僕は正統な進化だと思うな。 M-1『GIRL FRIDAY』はミディアムなパワーポップ・ナンバーなんだけど、イントロからギターソロからナックの『マイ・シャローナ』のパロディ。パロディしながらも、メロディはしっかりビークル節で、あの名曲に負けないくらい良質。奥田民生にもよくあるニヤリとさせるあの感じ。楽しいな、こういうの。M-2『DAMNATION』はストレートな疾走パワーポップ・ナンバー。間奏とかに進化したビークルを感じる。そしてM-3『FOLLOW ME』はPESELA-QUESELA-IN時代を思わせるような切なげなアコースティック・ナンバー。さりげないけどキーボードの入れ方とか凄く巧い。暴れたいだけの人にはこの曲は駄目かもしれないけど、こういう曲もあると勢いのある曲も活きてくると思うしいいんじゃないかな。これも進化。 まあでも、僕が進化と感じたことを退化と感じる人も中にはいるだろうけど、それはバンドが続いていくことで仕方ないことなんじゃないかな。僕はこれからの活動が楽しみ。 |
 |
BEAT CRUSADERS 『SENSATION』 |
タワレコ限定発売だったシングル『GIRL FRIDAY』に続いて、今度は全国リリースされた3曲入りシングル。 メンバーが変わっても、ビークルらしさは健在。ギターポップ、パンク、エモ、そしてモータウンまで呑み込んだポップ感と、思わず涙が出ちゃうような美メロがギュウギュウに詰まったシングルになっています。ポップかつエモーショナルに疾走するM-1『SENSATION』はやっぱりコブシを突き上げて一緒に叫びたくなっちゃうし、ややテンポを落としたM-2『TALKING IN YOUR SLEEP』で見せる曲展開やアレンジは、その辺の勢いだけのバンドには真似できない。モータウンのリズムを導入したポップ・チューンM-3『LAST MINUTE』には思わず笑顔。 やっぱりビークルは相変わらず素敵だね。ただ、この3曲って個人的にはキラーチューンって感じじゃないし、新しいビークルってわけでもないのね。アルバムに入ってたらいい感じの曲だと思う。これをわざわざシングルでリリース必要はあるのかなあ。 |
 |
BEAT CRUSADERS 『A PopCALYPSE NOW〜地獄のPOP示録〜』 |
ビートクルセイダーズのメジャーデビュー・ミニアルバム。もともと死ぬほどポップな音を鳴らし続けてた彼らだし、メジャーデビューしても特に大きく変わったことはないです。やっぱり死ぬほどポップ。アホみたいに美メロ。 ただ、インディーズ時代とメンバーが変わってリズムやキーボードアレンジ、コーラスワークがグンとハイプ化されたような印象です。旧メンバー時代の曲のリメイクも2曲収録してるんで、以前からのファンは聴き比べてみると面白いんじゃないかな。ただ、宅録的なチープさが少し薄れた感じもするんで残念に思う人もいるかも。あと何が残念かってインディーズ時代のベスト盤に続いてCCCDなところ。 |
 |
BEAT CRUSADERS 『P.O.A. 〜POP ON ARRIVAL〜』 |
ビークル、メジャー初のフルアルバム。シングルになってた『HIT
IN THE USA』、『FEEL』、ミニアルバム『地獄のPOP示録』に収録されてた『JAPANESE
GIRL』、『LOVE DISCHORD』も収録。アンチCCCDで聴けなかった人も今作は普通のCDなんで安心です。初回盤はボーナストラックを2曲収録してるんで、お早めに。 内容のほうは相変わらず、何も考えずに楽しめるポップナンバーがズラリ。ベスト盤かよってくらいにキラーチューン満載。80年代フレーバーたっぷりのポップパンク・サウンドにキラキラした極上メロディ、切なくエモーショナルなボーカル、遊び心も忘れてません。インディーズ時代=前メンバー時代と比べるとメロディはよりポップにキャッチーになったような印象かな。だけど、前メンバーの頃よりもリズム隊がガッシリしてるんでペラペラなポップスにはなってません。キーボードは以前にも増してカラフルに暴れまくってるんで、最近のムーグを捨てちゃったウィーザーにガッカリしてた人も満足できる作品かもしれないです。ポップでポップでポップな傑作。エモな音を求めてる人には少し物足りないかもしれないけど、とにかくポップな音が好きな人は是非是非。 |
 |
BECK |
マンネリ化しつつあったロック界に新風を巻き起こしたBECKの2ndアルバム。生演奏とサンプリングでBECK独特の世界を作り出している。一言で言うとロックとヒップホップの融合。間違いなく90年代で最も重要なロックアルバムの一枚。 |
 |
BECK 『GUERO』 |
なんか立ち読みした雑誌でベックの新作は「オディレイとシーチェンジの良いとこ取り」みたいなことが書いてあったんで、ちょっと楽しみにしてたんだけど、たしかにそんな感じ。遊び心いっぱいのオディレイにシーチェンジばりのメロディを持ち込んだ作品だと思います。 でも、正直ちょっと物足りないんだよなあ。『オディレイ』はあの時代に出たからこそ良かったのかなあ。今作を聴いてると実験性や遊び心が『オディレイ』のときのまま止まってるというか凄く古臭い印象を受けちゃったんだよね。いや、それなりに新しいことはやってるかもしれないけど、既にフォロワーにやり尽くされちゃってるというか。それでもメロディが飛びぬけて良ければ問題ないと思うんだけど、そういうわけでもなくて。いや、普通に良い作品なんだろうけどね、それでも歴史に残るような作品を作ったBECKにはもっと上を求めてしまう。 |
 |
BENNIE K 『サンライズ』 |
最近、この曲が頭の中で流れまくりです。キラキラしたポップロック・サウンドに乗せて流れていく、とびっきりキャッチーなメロディの歌パートとパンチの効いたラップのソロパート、スリリングなラップの掛け合い。転調部分では切なく歌い上げ、間奏ではコール&レスポンス。アウトロでは変則ビートも飛び出してもう盛り沢山。たった4分間の中にこれでもか!ってくらいに色んな要素を詰め込まれてて聴けば聴くほど楽しいポップソングです。これだけ詰め込んでも全然くどくないどころか、心地良くポップ&キャッチーに仕上げてるのがホントに凄いと思う。最初から最後まで全部がサビみたいだし。この曲を作曲&編曲したMINE-CHANGって人はタダ者じゃないね。大塚愛の『さくらんぼ』もある意味、究極のポップソングだと思ったけど、この曲も負けてないです。 ちなみにBENNI Kは留学先のロサンゼルスで出会ったボーカルのYUKIとラッパーのCICOが帰国後に結成した女性ヒップホップ・ユニット。この曲がデビュー曲かなって思ってたんだけど、実はもう8枚目のシングルなんだね。アルバムも既に2枚リリースしてたり。これまではベタなR&B系の音をずっとやってきたみたいだけど、個人的には『サンライズ』みたいな路線で進んでいって欲しいなあ。カップリングのR&B曲も微妙だし。 |
 |
BENNIE K 『DREAMLAND』 |
コカコーラのCMでもお馴染みのベニーKの9枚目のシングル。『サンライズ』は大好きで次に出たアルバムを聴いて、普通の歌謡R&Bばっかりで少しガッカリしたんだけど、今回のシングル『DREAMLAND』は『サンライズ』みたいにMIXED
BAG(ごちゃ混ぜ)な感じで、それでいて思わず口ずさみたくなるようなキャッチーなサビがクセになる良質ポップソング。『サンライズ』を初めて聴いたときのような衝撃はないけど、トラックの出来も抜群だし、YUKIの歌もCICOのラップも文句なしにかっこいい。 カップリングのほうはタイトルトラックに比べると少し地味だけど、『サンライズ』や『DREAMLAND』みたいな曲ばかりだとクドすぎるし、このくらいのバランスでちょうどいいかもね。カップリングでもやっぱり2人の歌声は素敵。 |
 |
BERG SANS NIPPLE 『MUSIC FOR THE SHORT FILM MARIE-MADELEINE』 |
今L'ALTRAのサポートメンバーでもあり、元BRIGHT
EYES、元SONGS:OHIAという経歴の2人組、BERG
SANS NIPPLEが1stアルバム以前にリリースした『MARIE-MADELEINE』って作品のサントラ盤。 サントラっていうこともあってか、1stアルバムと比べると少し落ち着いた雰囲気のインスト作品になっています。ヴィブラフォン、グロッケン、マリンバ、スティールパンなどがキラキラ奏でる美しい音世界。ちょっと民族っぽさもあって、まるで、どこか南の島の満天の星空の下にいるような気分。メロディもホント良いんだ。個人的に最後の曲の男性ボーカルは入らなかったような気がするけど、大好きな作品。ASANA、MICE PARADE、SACK&BLUMMあたりを好きな人はきっと気に入ると思うな。 |
 |
BERG SANS NIPPLE 『FORM OF...』 |
BERG SANS NIPPLEの2003年発表の1stアルバム。ヴィブラフォン、グロッケン、マリンバ、スティールパンなどをメインにしたインストっていうのはサントラのほうと変わらないんだけど、こっちは電子音率が高め。程よく甘くて、程よくゆるい。そして最高に美しい。音色やメロディもいちいち素晴らしいし、生音と電子音のバランスもホントに絶妙です。盛り上るところはしっかり盛り上って、マッタリするところはしっかりとマッタリ。アルバムの流れもいい感じ。なんか褒めてばっかりだけど、本当に良いんだから仕方ない。これを聴いたのは2004年の初めだけど、2003年ベスト50の上位10位以内に入れたかったな。 L'ALTRAから、ASANA、MICE PARADE、SACK&BLUMMAなんかを好きな人は是非是非。生音系エレクトロニカを好きな人にもお薦めです。本当に大傑作。 |
 |
BEYONCE 『DANGEROUSLY IN LOVE』 |
米国の女性R&Bグループ、DESTINY'S CHILDの中心人物、ビヨンセ・ノウルズのソロ作品。2003年リリース。もともとアーティストというよりもアイドル的な色が強く、映画『オースティン・パワーズ
ゴールドメンバー』で本格的なスクリーン・デビューも果たした彼女だけど、今作ではほとんどの曲を自身で書き、プロデュースにも参加。ビヨンセのアーティストとしての存在感を示した作品となっています。ちなみにこの作品、2003年のアカデミー賞で「最優秀女性R&Bパフォーマンス賞」、「最優秀コンテンポラリーR&Bアルバム賞」を受賞。さらには、ルーサー・ヴァンドロスとのリメイク『THE
CLOSER I GET TO YOU』で「最優秀R&Bグループ・パフォーマンス賞」、ボーイフレンドのジェイ・Zをフィーチャーした『CRAZY
IN LOVE』では「最優秀ソング賞」と「最優秀ラップ・コラボレーション賞」を受賞とアカデミー賞最多5部門で受賞というとんでもない作品です。 とにかく、その「最優秀ソング賞」を受賞したM-1『CRAZY IN LOVE』が最高。攻撃的なヒップホップ・トラックにシャイ・ライツのゴキゲンなホーン・サンプルとビヨンセ&ジェイ・Zのラップが絶妙に絡み合ってガツンとくる。ミーハーと言われようが何と言われようがカッコいいものはカッコいい。続く、中近東の香りがするR&BナンバーM-2『NAUGHTY GIRL』と同じく中近東な雰囲気でショーン・ポールのラガ・テイストなラップをフィーチャーしたM-3『BABY BOY』も秀逸な出来。その次のアウトキャストのビッグボーイとコラボしたM-4『HIP HOP STAR』も素晴らしい。ディストーション・ギターもフィーチャーした攻撃的なトラックにビヨンセの囁くようなセクシーボイス。もうゾクゾクしまくり。ここまでの4曲は完璧だと思う。 ただ、それ以降の曲は無難なトラックが多く、しっとりとしたR&Bバラードばかりなのでちょっと退屈。もうちょっと後半にも面白いトラックの曲や攻撃的な曲があっても良かったのになって思う。ちょっとエレクトロニカ風なトラックのM-7『YES』なんかは新鮮でいい感じだし、M-8『SIGNS』のビヨンセとゲストのミッシー・エリオットの美しい掛け合いにはため息出まくりだし、M-12『DENGEROUSLY IN LOVE 2』なんかは名曲だと思うけどね。 まあ、アルバムとしては残念な部分もいっぱいあると思うけど、個々の曲のクオリティはやっぱりそれなりに高い。ここに収められてる歌、楽曲、トラックを聴くと、やっぱり日本のR&Bはまだまだだなーって思わずにはいられないよ。 |
 |
B.FLEISCHMANN |
ドイツのエレクトロニカ・ユニット。 |
 |
B.FLEISCHMANN 『WELCOME TOURIST』 |
MORR MUSICの41作品目はMORR MUSICの記念すべき第1弾アーティスト、B.FLEISCHMANNの2枚組大作アルバム。 最近のMORR MUSICはTIED&TICKLED TRIOのジャズ作品はなかなか素晴らしかったものの、後は猫も杓子も同じような面白みのないギターポップばかりで迷走してるなって感じだったんだけど、今作はみんなが思い描いてる理想のMORR MUSICをそのまま音にした感じの甘く美しい純粋なエレクトロニカ作品になっている。生音とエレクトロニクスによる美しくメランコリックなサウンドスケープ。絶妙に心地いいビート感。適度のポップ感。アルバム全体を通してのドラマチック感。まるで色んな国々を旅しているようなバラエティ感。そんな素敵な11曲が収められたDISC1も素晴らしいんだけど、45分の大作を収録したDISC2が本当に素晴らしい。もう素晴らしすぎて45分でも足りないくらい。褒めたいところはいっぱいあるけど、特にピアノやサックスの使い方が絶品。これはエレクトロニカ好きな人はもちろん、ポストロック好きな人やスロウコア好きな人にも聴いて欲しいな。大傑作。 ホントこういうのが聴きたかったんだよ。MORR MUSICがもっとこういう作品をリリースしてくれれば、エレクトロニカを一時的なブームで終わらせないで済むと思うんだけどな。 |
 |
BIGGABUSH 『BIGGABUSH FREE』 |
UKダブ界の重要ユニット、ロッカーズ・ハイファイのメンバーだったビッガーブッシュのファーストアルバム。レゲエから、ヒップホップ、ハウスまで曲によって多様に変化するブレイクビーツに、ひたすら深く重く響き渡る重低音ベース、その上をドラッギーでトビトビな上ものが飛び交って、髪の毛の先からつま先までを最高に気持ち良くしてくれます。ダブ特有のスモーキーな空気感や腰にズンズン響くベースとハウスやヒップホップを経由したブレイクビーツの絡み具合が絶妙。 そして、全体の空気感は見事に統一されてるんだけど、ヒップホップ寄りな曲があったかと思ったら、ルーツ寄りな曲があったり、アンビエント寄りの曲があったり、女性ボーカルをフィーチャーした歌物まで登場したりと、飽きさせない構成もいい感じ。派手さや革新性はないけど、気持ち良さのツボを突きまくりなダブ・インスト集になってます。クラブ・テイストのダブが好きな人は是非是非。 |
 |
BJORK 『MEDULLA』 |
MATOMOSやHERBERTをゲストに迎えエレクトロニカ的手法を大幅に取り入れた前作『VESPERTINE』から3年ぶりとなるビョークの通産5作目。今作はロバートワイアット、マイクパットン、日本人ヒューマンビートボクサーのドカカなどをゲストに迎え、ほとんど人間の声のみで作られた実験性の高い作品になっています。声のみって言ってもコンピュータでエディットされまくってるから、「これも声!?」って音もいっぱい登場するんだけどね。 新しいことに挑戦してるわりには、あまり新鮮味が感じられなかったのは、あのビョークの個性的な歌声が前面に出てるからかな。どんなトラックをバックに歌ってもビョークはビョークでしかないというか。まあ結局は、前作の方法論はそのままにエレクトロニクスを声に置き換えただけだしね。『VESPERTINEその2』っていう印象。 実は個人的には『VESPERTINE』はあまり好きじゃないんだよね。めちゃくちゃ面白いことをやってるわけでもなく、ポップなわけでもなく、どっち付かずな感じが。同じようなことを感じる今作も正直あまり好きじゃないです。初期の3作みたいに前衛的なことに挑戦しながらも、ポップソングとして成り立ってたところが好きだたんだけどなあ。決して駄作じゃないけど、ビョークにはもっと上を期待しちゃいます。 |
 |
BLACK BOTTOM BRASS BAND 『ハッピー・ラッシュ!』 |
数多くのアーティストの作品やライブで名前をよく目にする、関西発ニューオリンズ・スタイルのブラスバンド、BBBBの7枚目のアルバム。 どこかのレコード屋で視聴したときに、このCDのポップに「超ハッピーなスカ・バンド」って書いてあったけど、スカじゃなくて基本はニューオリンズ・スタイルのブルース、ジャズ、ファンク。今作ではニューオリンズ・スタイルはもちろんラテンやロックンロール、レゲエまで、陽気で元気で爽快、もうとにかく大騒ぎ。ゲストで浜村淳!やウルフルズのトータス松本、RIP SLYME、玲葉奈、BEGINなども参加してパーティーパーティー。とってもハッピーハッピー。タイトル通り「ハッピー」。もうこのアルバムを説明するのは、この「ハッピー」の一言で十分。 1曲目で浜村淳も言ってるけど、このBBBBは昔は阪神ファンのダイブでも話題になった大阪道頓堀の戎橋(通称ひっかけ橋)で演奏してたりしてたらしい。こんな「ハッピー」な音楽が路上で流れてるって本当に素敵なことだな。僕はBBBBは見れてないけど、ちょっと前まで戎橋は音楽やアートで溢れてた。今は規制されてしまって、それらは消えてしまった。今あるのはキャッチをしてる色男とエセ阪神ファン。迷惑だとか邪魔だっていう人の気持ちも解るけど、僕は街中で音楽やアートが溢れることが好きだ。それって「ハッピー」なことだと思う。。それがBBBBみたいな音だったりしたら、とびっきり「ハッピー」。もっと「ハッピー」が街に溢れて欲しいな。 |
 |
BLACK DICE 『BEACHES AND CANYONS』 |
ニューヨーク出身の3人組、ブラックダイス。FAT
CATからリリースです。 サイケ、トランス、エレクトロニカ、ノイズ、ジャーマンロックなどを飲み込んだサウンド。心地よい浮遊感と、圧倒的なノイズ。美しいんだけど、暴力的。FAT CATらしく他にはない独自の音を聴かせてくれます。 BOREDOMS meets MY BLOODY VALENTINE meets CANって感じで、めちゃくちゃトライバルでカオティック。そして、神秘的。かっこいいです。BOREDOMS周辺が好きな人にお薦め。 |
 |
BLACK DICE 『CREATURE COMFORTS』 |
ブラックダイスのセカンド・フルアルバム。今作もリリースはFAT
CATからです。 相変わらず、唯一無二な音世界。前作と比べると暴力的な要素は若干減ったかな。ビートも控えめ。静かに壊れまくってます。民族音楽、サイケ、ジャーマン、トランス、ダブ、音響、ポストロック、エレクトロニカなどが不規則に、支離滅裂に混ざり合って、非常にカオティックな音世界を展開。グチャグチャでギタギタでノイズなんだけど、何故か、とっても美しい。この人たち、頭の中どうなってるんだろ。この感覚はなかなか味わえないね。個人的には暴力的な要素が減ったのが残念だけど、一度体験してみる価値はあるかも。 |
 |
BLAST HEAD 『HEAD MUSIC』 |
徳之島出身のDJ光、東京出身の岡村哲也によるユニット、BLAST
HEADの3rdアルバム。 1曲30分(クレジットは5曲)の大作。30分間、ダビーでトライバル、そしてミニマルな深いチルアウト空間が広がります。夜明けの海のような音楽。 |
 |
BLAST HEAD 『LANDSCAPE』 |
徳之島出身のDJ光、東京出身の岡村哲也によるユニット、BLAST
HEADの4thアルバム。 浮遊感のあるスピリチュアルなアンビエント・ハウスなビートに、民族音楽の要素を加えたようなサウンド。無機質なビートのなかに三味線やスライド・ギター、ハモンド・オルガン、サックスなどが鳴り響いて、ゆるくて深い音世界を作り出しています。 幻想的なダブ・エフェクトもいい感じ。晴れた日、どこか南の島の上空を飛んでいるような音。もうとにかく気持ちいい。めちゃくちゃヤバイです。BOREDOMSや、ROVO、CICADA、それからCALMやCHARI CHARIなんかを好きな人は必聴。かなりお薦めです。 |
 |
BLOOD BROTHERS 『CRIMES』 |
シアトルの5人組、ブラッドブラザーズの通産4作目。リリースはV2から。万人お断りな変態ハードコアです。ハードコアやパンクはもちろん、プログレもニューウェ−ブもポストロックもポストパンクもメタルもジャズもゴチャマゼのグチャグチャ。変拍子や転調は当たり前、むちゃくちゃな曲展開。ツインボーカルのうちの1人、ジョニー・ホワイトニーの絶叫はハイトーンを通り越してカートゥンネットワークの悪者級。かなりイっちゃってます。とっても暴力的です。でもメロディはキャッチーなおかげで意外とポップな感触。そのあたりも含めてホント変態的です、この人たち。個人的にはもうちょっと低音が効いてて欲しかったかな。それでも、この変態っぷりはその手の音楽が好きな人は聴く価値ありです。昔のボアダムスやボートが好きな人にお薦め。 |
| BLUEBEARD 『BLUEBEARD』 |
日本のエモコア・バンド。 まず、1曲目のインストがエモーショナルでメチャクチャかっこいい。演奏も巧い。で、2曲目、ボーカルの声が美しい。こういうジャンルには珍しいハイトーンの美しい声で伸び伸びと歌う。メロディは哀愁漂う感じ。ギターはエモーショナル。そして、うねるベース、タイトなドラム。 英詩なんだけど、メロディも凄く洋楽っぽい感じ。言われなかったら日本のバンドって分からないな。とにかく「美しい」って言葉がピッタリのエモ。TRAVISや初期RADIOHEADとかを好きな人にもいいかも。 |
|
 |
BLUR 『THINK TANK』 |
ギタリスト、グレアム・コクソンが脱退して、初のBLURのアルバム。通算7枚目。 名曲『SONG2』を彷彿させるような(もっとエレクトロクラッシュ寄りだけど)、ノーマン・クックのプロデュース曲、M-3『CRAZY BEAT』や、前作『13』に通じるようなメロウ・チューン、M-10『SWEET SONG』など今までのBLURを彷彿させる部分はあるんだけど、マリ音楽に近づいてたり、GORILLAZっぽかったりと、かなりデーモンのソロ・ユニットみたいに感じた。もともと、グレアムはあまり好きじゃなかった僕にはちょっと嬉しい変化。でも、グレアムを含めてBLURが好きだった人には、ちょっときつい作品だと思う。 全体的にリズムや民族音楽を取り入れたアレンジが面白い。それでもマニアックに走りすぎずに凄くポップ。『13』よりも遥かにポップ。『SONG2』や『BOYS & GIRLS』、『TENDER』みたいな圧倒的な名曲は正直ないんだけど、全体的な流れが良くて、僕は結構好きな作品。 ブリットポップみたいなのを好きな人より、どっちかと言うとGORILLAZやデーモンのマリ・ミュージックが好きな人にお薦めかな。あと、このアルバムはCCCD。US盤は普通のCDなんで、買うんだったらそっちを。 |
 |
BOARDS OF CANADA 『MUSIC HAS THE RIGHT TO CHILDREN』 |
98年発表のBOARDS OF CANADAの2ndアルバム。 |
 |
BOARDS OF CANADA |
スコットランド出身のエレクトロニカユニットの3rdアルバム。WARPからのリリース。リズミカルなヒップホップビートに温かみのある電子音が絡み合って、何とも言えない哀愁感が漂っている。ハンドクラップや声の使い方も上手い。目を閉じて聴くと、ゆがんだ幻想の世界が広がります。何とも言えない浮遊感。優しく暖かい。日々の喧騒から抜け出す至福の時。 |
 |
BOaT 『FRUITS☆Lee』 |
男2人、女3人(内1人は中国人)からなるバンド、BOaTのインディーズの初音源。日本語、英語、中国語、ギターポップ、パンク、メタル、オルタナ
etc.なんでもあり、変拍子&転調ありまくりのひねくれミクスチャーポップ。 |
 |
BOaT |
僕の心のベスト10第1位なバンド、BOaTのインディー2作目。 |
 |
BOaT 『LISTENING SUICIDAL』 |
BOaTのメジャー1作目、通算3作目のアルバム。変態アレンジは健在。今作ではポップ度が少し減って、ロック、プログレ寄りのサウンドになった。センチ度は倍増、極上のメロディで泣ける泣ける。こんなにアレンジが変態的で、メロディが極上なバンドは他になかなか無いです。 |
 |
BOaT 『RORO』 |
BOaTのメジャーデビュー後2作目です。初めてストリングスも導入、インストゥルメンタル曲へのアプローチ、前作までの多面的な音楽性をより深く進化させ生まれた作品です。上の『FRUITS☆Lee』とは全く違うバンドのよう。 |
 |
BOB LOG III 『SCHOOL BUS』 |
ジャンク・ブルース・デュオ、DOORAGの片割れ、ボブログ三世の1stアルバム。 ドラムマシンにあわせてギターを弾き、足でバスドラを叩く。そして、電話の受話器を組み込んだヘルメットで顔を多い、エフェクター処理された声で歌う。そんな奇抜な姿で奏でるサウンドは、ローファイぎみなブルーズ・ロック。 一聴した感じはチープなんだけど、よく聴くと凝ったことをしてます。ジョンスペとか好きな人にお薦め。ただ、この人の音はCDを聴くより、実際に動いてるところを見たほうが楽しめると思うな。 |
 |
BOB LOG III 『TRIKE (町でいちばんの三輪車)』 |
ボブログ三世の2ndアルバム。 ベック、ソニック・ユース、ウィーン、ボアダムス等とツアーをした成果か、曲のクオリティが凄く高くなった。前作よりロックンロール。メロディは少しポップになった。 おっぱいをパチパチ鳴らす曲があったり、馬鹿バカしさはそのまま。メチャクチャ楽しい、お気楽ロックンロール・アルバム。ジョンスペ好きや、昔のベックが好きだった人にお薦めです。 |
 |
BO GUMBOS 『ボ&ガンボ』 |
惜しくも急遽してしまった、どんと率いるボ・ガンボスの89年にリリースされたデビューアルバム。解散から10年経った2005年にはUAやYUKI、奥田民生、YO−KING、トータス松本などが参加したトリビュート盤がリリースされたりトリビュートライブが行われたりしてたけど、このボ・ガンボスは早すぎた良バンドのひとつだと僕は思います。ニューオリンズの音楽への愛が溢れるファンク・サウンドに日本のフォーク経由の切ないメロディ、日本語を大切にした歌詞。ファンキーなリズムにブギウギピアノが最高に楽しい。ソウルフルなどんとのボーカルもゴキゲン。今、聴いても十分にかっこいいというか、聴かれる音楽が多様化してきた今だからこそ多くの人に聴いてもらいたいバンドです。くるりとかZAZEN
BOYZなんかを好きな人にも十分にアピールできるんじゃないかな。 ボ・ガンボスは解散までに数枚、アルバムをリリースしてるんだけど、個人的にはこのデビューアルバムが断然お薦めです。解散後にリリースされたソウルフラワーユニオンの中川敬選曲のベスト盤もこのアルバムから最も多く選曲されてます。お祭り騒ぎの曲もホント楽しいし、バラードは泣ける。『トンネルぬけて』は名曲だね。 |
 |
BOMB THE BASS vs LALI PUNA 『CLEAR OUT』 |
87年にデビューして、トリップホップやビックビートなどの先駆け的サウンドをやってきたベテランのBOMB
THE BASSとMORR MUSICのエレクトロニカ・ポップ・ユニット、Lali
Punaとのコラボレーション。 硬質なブレイクビーツに女性ボーカル。OPIATEやAROVANEなどのリミックスも収録してるけど、MORR MUSICサウンド、ど真ん中のHERRMANN&KLEINEのリミックスとオリジナル・ミックスが個人的には良かった。でも、トータルするとちょっとイマイチかも。 |
 |
BOOM BIP & DOSE ONE 『CIRCLE』 |
アンチコンの中でも個性的なDOSE ONEと、ジャズ・ブレイクビーツを作り出すBOOM
BIPのユニット。 幻想的でジャジーなエレクロニカ的なトラックに、甲高いMC。2,3分の曲が29曲。次々、違う音が出てきておもちゃ箱みたいで楽しい。凄く実験的なヒップホップなんだけど、肌触りは凄くポップです。 アンチコン周辺の音が好きな人や、MACKA-CHINやイルリメを好きな人にお薦め。 |
 |
bonobos 『HEADPHONE MAGIC』 |
EGO-WRAPPIN'のオープニング・アクト、COPA
SALVO等との共演などもしている、大阪の男女4人ダブ・ポップ・バンド、ボノボの1stミニアルバム。ダブ、レゲエ、ボサノヴァなどをベースにした演奏に、甘く美しいボーカル。初期FISHMANS、POLARISを彷彿させるようなサウンドなんだけど、こっちはもっとラテン寄り。凄く心地良いです。 甘くまったりした曲も良いけど、軽快でめちゃくちゃポップなラテン“うたもの”、M-1『MIGHTY SHINE,MIGHTY RYTHM』が最高。これからが凄く楽しみなバンドだな。初期フィッシュマンズ、ポラリス、あと、ロッキングタイムやマイスティースなんかを好きな人にお薦め。 |
 |
bonobos 『もうじき冬が来る』 |
bonobosのメジャーデビューシングル。bonobosはサウンド的に大きく分けるとFISHMANSフォロワーになっちゃうかもしれないけど、FISHMANSよりもずっとカジュアルだし音の幅も広いね。 M-1『もうじき冬が来る』は思わずスキップしたくなるような、陽気で軽快なポップ・ナンバー。グルーヴィーで高揚感のある演奏に、暖かく伸びやかなボーカル。そこにEGO-WRAPPIN'やCOPA SALVOのサポートも務める武嶋聡による素敵なフルートも加わって幸福感いっぱい。M-2『SUNSET:SUNRISE』はスロウで隙間いっぱいのダブポップ。ゆらりゆらりゆるりゆる〜り。M-1とは全くタイプの違う曲だけど、これがまた良い。M-3『カサはいらないよ(DEMO VERSION)』は、シンプルでアコースティック、しっとりとしたナンバー。DEMO VERSIONってことで音質とかは決して良くない。個人的にはCDにDEMO VERSIONを入れるのはあまり好きじゃないけど、いい曲なことは確か。完成版が楽しみだ。そしてフルアルバムが待ち遠しい。 |
 |
bonobos 『HOVER HOVER』 |
ボノボの1stフルアルバム。レゲエ、ダブ、ラテン、カリプソなどワールド・ミュージック色の強いサウンドに儚くゆらめくハイトーン・ボイス。腰にくる重低音ベースを核とした演奏もいいんだけど、なんと言ってもボーカルの蔡忠浩の歌声がいい。消えそうなくらいに澄んだその歌声は、楽しいときも悲しいときも、朝も昼も夜も、どんなときにでも、違和感なく聴く者の身体に溶け込む。楽曲はシンプルでアコースティックな歌物から、10分近くあるスロウなダブポップ、ほのぼのとしたカリプソ、そして、思わず踊りだしてしまいそうな陽気なダンス・ナンバーなどなど幅広く、それぞれ完成度も高い。 個人的には、幸福感いっぱいのM-2『もうじき冬が来る』、程よい疾走感で躍動感と開放感いっぱいのダンサブルなナンバーM-3『ライフ』、少し早めのテンポと浮遊感が最高に心地良いダブポップ・ナンバーM-4『MUSIC』、ボノボのメロディと歌声の良さが堪能できるシンプルなフォーク・ナンバーM-6『I TALK』、ゆらゆらふわふわ漂う音世界にいつまでも揺られていたくなるスロウなダブポップ・ナンバーM-8『HOVER HOVER』、嫌な気分もどこかにいっちゃうようなカリプソ・ナンバーM-10『WATER』あたりが良かった。このバンドはスロウな曲よりも軽快な曲のほうが好きかな。スロウな曲はもうちょっとメロディにメリハリが欲しい。 きっと何かに似てるとか言う人もいるだろうけど、いいものはやっぱいいよ。それにこれは決して、ただの真似ごとなんかじゃない。敢えて比較はしなかったけど、じっくり聴いたら分かる。ボノボはボノボ。ルーツへの愛はたしかにいっぱい感じられるけどね。 |
 |
bonobos 『あの言葉、あの光』 |
ファーストアルバム以来となるボノボの3曲入りシングル。タイトルトラックは夏の終わりにピッタリの哀愁いっぱいな極上ミディアム・ラヴァーズ。これまでは全てセルフプロデュースだったボノボだけど、今回のタイトルトラックではレゲエの大先輩で、UAの『情熱』や『雲がちぎれるとき』、『甘い運命』、『スカートの砂』など、彼女のヒット曲のほとんどでプロデュースを手掛けていた朝本浩文をプロデュースに迎えています。これまでのボノボもそれなりに良い音楽をやってきたと思うんだけど、どこか自分たちのカラにこもってたような印象があるんだよね。今回の朝本浩文のプロデュースはそのカラを見事に破って、外に向けた音に磨き上げてるような印象。外に向けたと言っても決してボノボらしさを捨てて売れ線に走ったとかじゃなくて、ただただボノボの魅力を最大限に引き出した好プロデュース。カップリング2曲はボノボのセルフプロデュースで、それはそれで良さがあると思うけど、比べちゃうといかに朝本浩文のプロデュースがうまくいってるかが分かるね。 この『あの言葉、あの光』、本当に素敵だよ。温かくて切なくて踊れて。上述したUAの名曲たちにも全然負けないと思うし、ボノボにしかできないボノボならではの曲だと思う。マイスティース好きな人もロッキングタイム好きな人も、そしてフィッシュマンズ好きな人も、泣いて泣いて踊れる名曲です。 |
 |
BOREDOMS 『SUPER ae』 |
日本人なんだけど日本より外国でのほうが人気のある?ボアダムスの大名盤。スーパーアーと読みます。ボアダムス関連の音源の中では割と入りやすい作品だと思うんで今まで聴いたことが無いんなら、このアルバムから聴くといいと思います。 サウンドはトランシーでサイケでアヴァンギャルドなロック。目を閉じて聴くと色んな世界がばーっと広がります。海から始まり、宇宙に旅立ったり、異国で民族の祭りに遭遇し、最後は再び静かに海に還っていきます。自然の壮大さを感じることができます。ドラッギーで中毒性があり、かなりクセになります。大傑作!!! |
 |
BOREDOMS 『VISION CREATION NEW SUN』 |
99年の作品。宇宙っぽくもあり、地球の自然も感じる。全く新しい次元に突入した作品。入り込むと、方向も何もかも分からなくなるような音空間。 |
 |
BOREDOMS |
スーパールーツ・シリーズの7作目。 |
 |
BOREDOMS |
スーパールーツ・シリーズの8作目。 |
 |
BOREDOMS |
ボアダムスの過去の音源を再構築するリボア・シリーズの最終作。 |
 |
BOREDOMS 『SEADRUM/ HOUSE OF SUN』 |
最近、V∞REDOMES名義での活動が目立ってた彼らだけど、BOREDOMS名義で前作から約5年ぶりとなるリリース。2曲で43分収録しています。1曲目の『SEADRUM』はパーカッシブなリズムが疾走し、ピアノが暴れまくり、ヨシミの声が右に左に乱れ飛ぶトライバルなナンバー。時には激しく時には穏やかにどこまでも壮大でどこまでも神秘的に、題名通り、まるで海のような音世界を繰り広げています。こっちはちょっとV∞REDOMESっぽいね。2曲目の『HOUSE
OF SUN』は攻撃的な1曲目から一転、ゆったりとゆるやかにたゆたゆとシタールや山本精一らしいギターの神秘的な音色がアンビエントに浮遊するナンバー。こちらも題名通りで日の出みたいなイメージかな。日の出の瞬間をスローモーションで見ている感じ。 どちらの曲もボアダムスらしいというかEYEらしい曲で、やっぱり凄い作品になってると思うんだけど、個人的に前作や前々作ほどの衝撃はなかったかな。予想範囲内の音というか。それでも素晴らしいと思うのはボアダムスがただ衝撃的で刺激的な音を作ってるだけでなく、ちゃんと響いてくる音を作ってる証拠だね。 |
 |
BOSSA PIANIKITA 『ピアニダージ』 |
プロのピアニカ演者のピアニカ前田、ポラリスとしても活躍中の坂田学、元KUSU
KUSUのメンバーで、現在はCOROCOVADOのメンバーでもある宮田誠、モンド・グロッソなどとの活動でも知られる田中義人の4人によるバンド、ボッサピアニキータの2ndアルバム。 ピアニカ前田のソロやピラニアンズではストレートなボッサやダブが多かったんだけど、ここで流れてくるのは音響やダブを通過した実験的要素の高いボサノバ。程よくポップで、程よくアヴァンギャルド。そして滅茶苦茶ピースフルで、滅茶苦茶ココチ良い。小気味の良いドラムに、美しく軽やかなギター、その上を行くピアニカの素朴で、どこか切ない音色が堪らなく良いです。じっくり聴き込むのも良し、ほんのり体を揺らすも良し、BGMにも良し。ホントに日本人はこういうインスト・ミュージックを作るのが巧い。 ACOUSTIC DUB MESSENGERSやピアニカ前田のソロが好きな人にお薦め。あとポラリス好きな人にもお薦め。ホント良いよ。 |
 |
BP 『ゴールデンBP』 |
現COALTAR OF DEEPERSのイチマキさんが在籍してたバンド。98年に解散してます。このアルバムは唯一の単独作品。COALTAR
OF DEEPERSと同じレーベルからのリリース。 |
 |
BRAHMAN 『THE MIDDLE WAY』 |
ボーカルのトシロウがモデルのりょうと結婚したり、北京のロックフェスに出演したときに現地のロックファンに石や卵を投げつけられ「帰れ」コールをされちゃった事件など色んなことがあったブラフマン、前作『A
FORLORN HOPE』から約3年ぶりとなるメジャー2作目のフルアルバム。前作はメジャーデビュー作にしてオリコン初登場2位。それ以降、3年間もアルバムをリリースしないなんて普通は考えれないことだけど、それを許してしまうトイズファクトリーには好感が持てるね。バンプにしてもケツメイシにしてもミスチルにしてもそうだけど、トイズファクトリーって凄くアーティストを大切にする印象。 前置きはその辺にして、この作品なんだけど、『A FORLORN HOPE』の延長線上のサウンドというか、ブラフマン以外の何者でもないサウンドです。昔みたいな民俗音楽的な要素はほとんどなくなっちゃったけど、前作で見せた感情的な音にインディーズ時代にあったハードコア的要素が戻ってきた感じ。独特な詩世界と深みのある演奏、感情的なボーカル、静と動を巧みに使い分ける唯一無二のロック・サウンドを展開しています。個人的にはインディーズ時代の『A MAN OF THE WORLD』に思い入れが強く、前作と比べてもキラーチューン的な曲が少なく感じるのもあって、今作を最高傑作とは言い切れないけど、このブラフマン以外に鳴らせない音世界は一度は聴いてみる価値があるんじゃないかなって思うよ。 |
 |
BRIAN WILSON 『SMiLE』 |
ビーチボーイズの歴史的名盤『ペットサウンズ』の後に制作されてたんだけど、未完成のままに終わってた幻の作品が37年の歳月を経て、ブライアン・ウィルソン自身の手で完成。いろいろ歴史のある作品だけど、そんな歴史は無視して、ただ単純に素晴らしい音楽作品だと思う。 基本的なサウンドは『ペットサウンズ』の延長線上かな。圧倒的なまでに計算され構築され尽くした声のマジック。あまりに美しすぎる音響世界。音楽に完璧なんてないのかもしれないけど、限りなく完璧に近い音響世界だと思う。ヘッドホンで大音量で聴かなきゃ損だよ。メロディも秀逸。あと今作は3部構成で組曲みたいになってるんだけど、全体の構成が本当に素晴らしい。ありふれた表現だけど、まるで一つの映画を観てるような。シャッフル演奏は禁物です。音楽の聴き方なんて自由だけど、この曲順で最初から最後まで聴いてこそ初めてこの作品の本当の魅力が伝わる気がするんだよね。逆にリピート演奏は推奨・・・しなくても自然とリピートしちゃうか。何度も何度も聴きたくなる新鮮味と37年後でも通用するような普遍性を兼ね備えた傑作です。 |
 |
BRIGHT EYES 『LIFTED OR THE SRTORY IS IN THE SOIL,KEEP YOUR EAR TO TE GROUND』 |
CONER OBERSTの1人ユニット、BRIGHT EYESの4枚目のアルバム。前作まではBECKに通じるような、ローファイなひねくれ宅録ポップって印象だったんだけど、今作では、バイオリンやチェロ、トランペットなど生音をふんだんに取り入れて、ボーカルも力強くなって、よりドラマッチックでドリーミーな音世界になっている。ドリーミーなボブ・ディランって感じ。 |
 |
BRIGHT EYES 『I'M WIDE AWAKE, IT'S A MORNING』 |
ブライトアイズの新作はアコースティックにこだわって作ったフォーク/カントリー路線の今作とデジタルを交えて作った『DIGITAL ASH IN A DIGITAL URN』の2作同時発売。ここに収録されてる『LUA』はビルボードのシングルチャートで1位を獲得したんだとか。ここまで特別キャッチーなわけでもなく、飾り気のない地味な曲が1位を取っちゃうところにビルボードチャートの良心を見たよ。アルバムのほうも、地味ながらも大切に作られた純粋に良い曲がズラリと並んでます。悪く言えば、ボブディランやニールヤングそのまんまなんだけど、安心して聴ける、多くの人の心にストレートに届く作品だと思う。捨て曲なんてなくて起承転結もしっかりと。ボブディランやニールヤングと並べても遜色のない良盤だと思います。個人的には真面目すぎて少し退屈だったけど、『DIGITAL ASH〜』と一緒に聴くと全然、満足。いや、むしろ大満足。 |
 |
BRIGHT EYES 『DIGITAL ASH IN A DIGITAL URN』 |
いつだっけレコード屋で「BECK好きは激マスト!」ってポップを見て彼のファーストアルバムを買ったのは。そのときは所詮、二番煎じだなあくらいにしか思わなかったんだけど、気が付いたら本家と変わらないくらい好きになってたという。近い時期に発売されたBECKの新作『GUERO』とこの2作を比べたら、こっちのほうが好きだったりしてね。ホント素晴らしいです、コナー・オバースト君の才能は! で、この作品だけど、もう一枚のほうでアコースティックに振り切れちゃった分、これまで以上にデジタルな側面を前面に出した作品になっています。装飾や遊び心が多い分、彼の最大の魅力であるグッドメロディがかすれてしまうんじゃないかって心配だったけど、そんな心配はご無用。テクスチャを飾りまくっても、彼のメロディはそれに打ち消されることなく輝きまくってます。目新しさはそんなにないけど、打ち込みも無難に素敵で文句なし。2枚でひとつみたいな感じはどうしてもあるんで、気になった人は是非、2枚とも聴いてみてくださいな。 |
 |
BROADCAST |
WARPからリリースなんだけど、WAPRっぽくないサウンド。 女性ボーカルで甘く儚いドリームポップ。ステレオラブっぽい。1回エレクトロニカを通過してステレオラブに帰ってきた感じかな。 アレンジは当り障りなくキャッチー、トラックはさすがWARPって感じでかっこいいです。とにかくポップでこういうサウンドを好きな人には、堪らないんじゃないかな。でも、僕的には、ちょっと物足りなかった。もうひとひねり欲しかったかな。 |
 |
BROTHOMSTATES 『CLARO』 |
WARPからリリースのアンビエントなエレクトロニカ。 |
 |
BROWNIES 『星とケモノ』 |
シンガーソングライター、市橋秀哉の1人ユニット、BROWNIESの柏原譲(POLARIS、exFISHMANS)をプロデューサーに迎えたミニアルバム。 この作品には、柏原譲の他に茂木欣一(東京スカパラダイスオーケストラ、exFISHMANS)、HAKASE-SUN(exFISHMANS)、HONZI(FISHMANSのサポート・バイオリニスト)とFISHMANS好きには堪らないメンバーが参加。あと、DRACOの森本直樹も参加。 サウンドのほうは、やっぱりFISHMANSの影響を感じずにはいられないサウンドなんだけど、FISHMANSよりもっとポップス寄り。ボーカルの声も佐藤くんや、POLARISのオオヤユウスケに比べると、あそこまでハイトーンではなくて、もっと甘い声。ところどころでラップに似た歌い方をしている部分があったりして、BROWNIES独特のサウンドになっています。個人的には、HONZIの美しいバイオリンと甘い歌が交差するM-4『人は病む』が良かった。 |
 |
BUFFALO DAUGHTER |
シュガー吉永、大野由美子、ムーグ山本の日本人3人組。BEASTIE
BOYSのレーベル、GRAND ROYALから。 |
 |
BUFFALO DAUGHTER |
久々の新譜。グランドロイヤルがなくなってから初のリリース。ZAKのスタジオSTROBOでレコーディングしていて、やっぱり音がいいです。前作までにあった遊びの要素が無くなってメッセージ性の強いストイックな作品になっている。音作りは懲りまくっているが程よい隙間がある。 |
 |
BUFFALO DAUGHTER 『PSHYCHICK』 |
BUFFALO DAUGHTERの新作はCD-DAとSACDのハイブリッド盤で登場。普通にCDとしても聴けるけど、SACD対応プレーヤーに入れると、もっと高音質で聴くことができる。残念ながら僕はまだSACDプレーヤーは持ってないけど、音質を悪くしてまでプロテクトをかけるCCCDとは大違いだ。他のアーティスト、レコード会社も是非見習って欲しいな。 今作は前作よりもインプロ度アップ。ジャーマンロックや、テクノ、エレクトロニカ、フリージャズなどをBUFFLO DAUGHTER流に自由に料理。音のほうもホントにどこまでも自由。気持ちよいです。 とにかくキラキラしたBUFFALO DAUGHTER流ダンス・ナンバーM-1『CYCLIC』が最高。また1stアルバムに収録された『li303ve』の新バージョン『303 Live』も収録。その成長ぶりに驚かされる。 |
 |
BUMP OF CHICKEN 『FLAME VEIN』 |
メジャーからのシングル『天体観測』で一躍有名になったバンプ・オブ・チキンのインディーズ時代にリリースした作品。彼らのレビューをするに当たって彼らに近いサウンドのバンドを何個かあげようと思って考えたんだけど、これだ!というのが思い浮かばなかった。ダイナソーJR.やWEEZER、U2やUKギターロック・バンドに影響を受けてることは確かなんだけど何か違う。一番それらのバンドと違うのがボーカルの藤原基央が書く物語性の非常に強い詞世界。歌ってる内容は「今を生きるよ」みたいなベタな内容なんだけど、それをただそのままストレートに叫ぶんじゃなくて、彼独特の表現で物語仕立てに歌われる。わずか数分間だけど小説や映画に負けないような表現力と構成力、ドラマチック性を持った彼のストーリーテリングは本当に目を見張るものがあると思う。彼のストーリーテリング能力だけでも触れてみる価値は十分にあるんじゃないかな。 この作品は、1曲目『ガラスのブルース』の出だしの「ガラスの眼をしたネコは唄うよ」っていう意味深なフレーズにいきなり引き込まれて、「昨日よりマシなメシが食えたなら今日はいい日だったと」っていう表現に感動し、サビに行きつく前には完全に藤原基央の世界に入り込んでしまう。そして、サビでの「ボクはいつもチカラ強く生きてるよ」「ボクはイマをサケブよ」という前向きな言葉が強く強く心に響く。切ないメロディに乗って激しく激しく心に響く。文句なしの名曲だと思う。 2曲目以降も、エヴァンゲリオンの綾波レイに向けて「哀しい時は目の前で大声を出して泣いてよ」「うれしい時は目の前で両手叩いて笑ってよ」と歌うM-3『アルエ』、誰でも「時には勇者にでもなれるんだ」と歌うM-4『リトルブレイバー』、人生を野球にたとえて「普通に生きてりゃ誰だってライトを浴びる日は訪れる」と歌うM-5『ノーヒットノーラン』など名曲揃い。 何フレーズかここに引用した歌詞を見ても分かるように、この作品にはどこまでも前向きなメッセージが込められている。歌や演奏に関してもどこまでも前向きだ。お世辞にも演奏やアレンジはうまいとは言えない。演奏やアレンジに関して言えば、次作『THE LIVING DEAD』やメジャーデビュー作『JUPTER』のほうがずっと上だけど、このひたすらな前向きさが僕を惹きつけて離さない。 |
 |
BUMP OF CHICKEN 『THE LIVING DEAD』 |
2000年発表のインディーズ2作目。「いくつかの物語をプレゼントしてあげる」と歌われてるM-1『ORPNING』で始まり、「僕はもう行かなきゃ」というM-10『ENDING』で終わるこの作品は、「生きる強さ」をテーマにした8つの物語が連なって1つの大きな物語を形成する。前作がひたすら前向きな内容だったのに対し、今作の物語は悲しく重い。前作や『天体観測』みたいに気楽な気持ちで聴くことはできないけど、その分、心に残るものは大きい。
僕は藤原基央みたいに表現力豊かじゃないし、こんな陳腐な表現じゃ失礼かもしれないけど、この作品に収められた8つの物語のどれもが名物語=名曲だ。「こいつはひどいどこまでもうさんくさい安っぽい宝の地図 でも人によっちゃそれ自体が宝物」「ホントにデカい誰もが耳疑う様な夢物語でも 信じ切った人によっちゃ自伝に成り得るだろう」財宝を夢見て大海原に旅立つ一人の男にたとえて“信じる道”について歌うアップテンポなギターロック・ナンバーM-2『グングニル』、「君が強く望みさえすれば 照らしだそう 温めよう 歩くタメの勇気にだってなれるよ」暗闇の中でのランプをたとえに、夢や理想、愛、安心の類を手にする力は自分の中にあるものだと気付かせてくれるミディアム・ナンバーM-5『ランプ』、「やっぱり君は笑った 別れの傍で笑った つられて僕も笑った また会えるからって確かめるように」そんじょそこらの恋愛ドラマよりもずっとグッとくる恋の物語M-7『リリィ』なども本当に素晴らしいんだけど、最も素晴らしいのがM-6『K』。 世間から忌み嫌われていた黒猫の物語。孤独だった黒猫はある日、同じように孤独だった絵描きに拾われ、一緒に暮らしているうちに初めて優しさや温もりというものを知る。絵描きは黒猫に「黒き幸」ということで“ホーリーナイト(HOLY NIGHT)”という名前を付ける。絵描きは毎日、友達となった黒猫の絵を描き続け、黒猫は絵描きにくっついて甘えていた。しかし、不吉な黒猫の絵ばかり描いていた絵描きは貧しい生活に倒れてしまう。夢を見て飛び出した帰りを待つ恋人に手紙を届けて欲しいという絵描きの最後の頼みを聞いた黒猫は、忌み嫌われた自分にも意味があるのなら、この日の為に生まれてきたんだろうと満身創痍になりながらも遠くの恋人の家まで手紙を届ける。そして黒猫は・・・。手紙を読んだ恋人はもう動かない猫の名前にアルファベットをひとつ加えて庭に埋めてやる。曲名にもなってる“K”の文字を加えられた「HOLY NIGHT」=「聖なる夜」は「HOLY KNIGHT」=「聖なる騎士」となり永遠に眠る。・・・歌詞のことばかり書いたけど彼のボーカルの藤原基央の歌声も忘れちゃいけない。繊細さを持ちながらも非常に力強い歌声はドラマチックな曲の世界観をしっかりと表現し、聴く者の心にズッシリと響いてくる。この曲では悲しい物語と心に響く歌声が切ないメロディとドラマチックなアレンジでアップテンポに畳み掛けてくる。もう僕はこの曲を聴くと黒猫と絵描きが出会ったシーンからもう涙が止まらなくなってしまう。 まだまだ演奏はうまいとは言えないけど、音楽はうまけりゃいいってもんじゃない。それを差し引いても余りある魅力がこの作品には存分にある。ギターロックを好きな人は変な偏見を捨てて聴いてみる価値のある作品なんじゃないかな。傑作です。ただ、彼らの作品では毎度お馴染みの隠しトラックだけど、これはせっかくのM-1『ORPNING』から始まってM-10『ENDING』で終わる構成を崩すようで、無かったほうが良かったように思う。そこだけは残念。 |
 |
BUMP OF CHICKEN 『JUPITER』 |
『天体観測』が大ヒットを収めた後にリリースされたバンプ・オブ・チキンのメジャー1作目。『天体観測』はもちろん、スマッシュヒットした他のシングル『ダイアモンド』と『ハルジオン』も収録。この『天体観測』、『ダイアモンド』、『ハルジオン』の3曲はどれも適度にフックも効いたストレートなロック・サウンドでメロディはキャッチー。バンプ独特の詩世界は健在で売れて然るべき名曲だと思う。メロディや詩、演奏のバランスは『天体観測』が一番優れていて、これが一番売れたのは納得だけど、個人的には他の2曲のほうが好きかな。『ダイアモンド』のほうは歌詞がいい。何回転んでもいいさっていう割とありがちな内容なんだけど表現の仕方が素晴らしく、本当に心に強く響いてくる。強く生きなきゃって思える。そして、『ハルジオン』のほうは演奏がいい。特に後半の盛り上がりが素晴らしい。バンプを聴いて演奏の部分でいいなって思えたのは、この曲が初めてだった。 『ハルジオン』に限ったことではなくて、このアルバムで一番大きく変わった部分は演奏能力だと思う。それは、これまでのバンプとは少し違う雰囲気な1曲目の『STAGE OF THE GROUND』や3曲目の『TITLE OF MINE』を聴けば一目瞭然。開放感のあるギターサウンドとグルーヴィーなリズム隊。まるで90年代以降のU2を思わせるような深く広がりのある壮大な演奏を聴かせる。M-4『キャッチボール』やM-6『ベンチとコーヒー』、M-8『ベル』みたいなインディーズ時代に近い曲調の曲でも明らかに以前よりも演奏がまとまってるのを感じることができる。 ただ、前作のレビューで“音楽はうまけりゃいいってもんじゃない”って書いたけど本当にその通りでそれらの曲が良かったかと言えば、僕は首を傾げる。これはこれで悪くはないけど、なんかインディーズの頃の作品ほどはグッとくるものがないんだな。単純にメロディのクオリティが下がったっていうのもあるかもしれないし、物語性も少し薄れたっていうのもあるかもしれないけど、それ以上にこの作品ではインディーズ時代にあった純粋な真っ直ぐさが薄れてるのが大きいんだと思う。なんかこの作品は無理をして着飾ってる印象を感じた。普段、着ることのないスーツを着て普段は行かないような高級レストランでデートしてる感じ。そんなんじゃ自分本来の魅力を出し切れない。 個人的にシングル以外でいいなって思ったのはアルバム中、最も物語性の強い歌詞を持ったM-10『ダンデライオン』くらいなんだけど、この曲にしてもカントリー風のアレンジになんてしないで、インディーズ時代のようなストレートなギターロック・サウンドでアレンジしてたほうが、きっともっとグッときてたと思う。アルバムにバラエティ性を持たせるという意味では良いし、バンドを続けていく上で変化も必要だと思うんだけど、このバンドに関してはシンプルなギターロック・サウンドのほうが本来持ってる魅力をより発揮できると思うな。 彼らは『ダイアモンド』の中で「何回転んだっていいさ 何回迷ったっていいさ」と歌ってる。そう、これはまだ旅の途中。彼らがまだまだこれからのバンドだ。インディーズ時代の名作『FLAME VEIN』と『THE LIVING DEAD』を何度も何度も繰り返し聴いた僕はまた彼らが素晴らしい作品を作ってくれると信じてるよ。 |
 |
BUMP OF CHICKEN 『スノースマイル』 |
『JUPITER』から1年ぶりにリリースされたシングル。このタイトル曲『スノースマイル』はこれまでのバンプにはなかったタイプの曲だと思う。歌詞の独特の世界観は相変わらずなんだけど、アコギを基調としたアレンジのこの曲はメロディーは穏やかでインディー時代のような生き急ぐような疾走感や張り詰めた緊張感はない。学園祭の延長みたいなギターロックはここにはなくて、凄くスケールの大きさを感じる曲。コーラスが多重録音されてるとか、そんな単純な問題じゃなくてバンド自体のスケール感がグンと大きくなったような印象。 そんなこんなで初期からのファンにとっては賛否両論ある曲なんじゃないかな。これを進化と感じるか退化と感じるか。それは人それぞれだと思うけど、少なくとも深化してることは間違いないと思う。『JUPITER』では深化具合が少し中途半端に感じたけど、ここまで深化するんだったら、これはこれで良いんじゃない。ちなみに去年の某夏フェスでバンプを観たときに個人的に一番響いてきたのはこの曲だったり。「スノースマイル」のくせに真夏だったけど、それはそれで良かったよ。この曲の歌詞(物語?)はホント泣けるよ。いい曲。 |
 |
BUMP OF CHICKEN 『ロストマン/SAILING DAY』 |
『スノースマイル』からわずか3ヶ月というバンプにしては異例のペースでリリースされたシングル。1曲目の『ロストマン』はアコギで静かに始まり、後半は力強いバンド・サウンドと藤原基央のボーカルが一気に畳み掛けるスケールの大きな曲。ベースラインはズンズン体に響いてくるようになったし、ドラムは変拍子を使ってたりしてリズムがカナリ強化されたような印象。「調子はどうだい」という問い掛けで始まり、迷いながらも前に進もうとする歌詞もちょっと重過ぎるような気がしないでもないけど素晴らしい。個人的には『天体観測』以上の名曲だよ。何かを失ったことがある人はきっと響いてくるものがあるんじゃないかな。こんなにも正直で心に響く歌詞を書ける人はなかなかいないよね。この歌詞にこのサウンド、そしてあの独特の歌声。好き嫌いはあると思うけど、バンプってホントに唯一無二なバンドだと思う。 2曲目の『SAILING DAY』は彼らの十八番ともいえるアップテンポの疾走ギターロック。こっちもなかなか良いです。でも、個人的にはやっぱり『ロストマン』。某ロック雑誌なんかでは大げさに名曲だ名曲だって言ってたけど、それも納得。オリコン初登場2位も納得。中高生専用ってことは全然なくて、多くの人に響く名曲だと思う。イメージだけで聴かず嫌いしてる人は、もしかしたら損してるかもよ。 |
 |
BUMP OF CHICKEN 『オンリー・ロンリー・グローリー』 |
インディーズ時代の曲『アルエ』のシングルカットはあったものの、新曲としては『ロストマン』以来、1年4ヶ月ぶりのシングル『オンリー・ロンリー・グローリー』。『JUPITER』に収録されていた『STAGE OF THE GROUND』の延長線上にあるような開放感いっぱいでスケールの大きいロックナンバーなんだけど、今回はインディーズ時代にあったような心地良い疾走感もプラス。ここまでのバンプの集大成といってもいいような曲に仕上がっています。疾走感もグルーヴ感もバッチリ。歌詞は『ロストマン』ほどの重さはないけど、やっぱり気持ちを前に向けてくれる。インディー時代の曲みたいに「騎士」や「猫」などファンタジックな言葉は登場しないけど、本質は何も変わってないね。完全なるオリジナリティ。最近じゃ、バンプ・フォロワーみたいなバンドもいっぱい登場してきてるけど、もう他の追随は許さないね。今度リリースされるアルバムが楽しみ。 |
 |
BUMP OF CHICKEN 『ユグドラシル』 |
バンプのメジャー2作目。これは昔からのファンには賛否両論あるだろうね。初期の作品の大部分を占めていたアップテンポの曲はほとんど無し、アコギを使った曲が増加、バンプは演奏が下手って言われてた頃は遠い昔のような落ち着いた演奏、即効性を殺した深みのあるアレンジ、藤原基央は以前よりも言葉をハッキリと歌うようになった。これを進化と感じるか退化と感じるかは人それぞれだけど、変化したことは間違いないね。 ちなみに僕は進化したように感じたよ。だって、これまでのどの作品よりも藤原基央の書く言葉が真っ直ぐに伝わってくるんだもん。いろいろと変化してる中でも、初期の作品からずっと貫かれてきたメッセージが歌詞カードを見なくてもガンガン伝わってくる。以前よりもギラギラ輝きを増した言葉がザックザック胸に突き刺さる。4曲目の冒頭なんて「人間という仕事を与えられてどれくらいだ」だよ。もうやられまくり。心に残りまくり。メロディも深みを増して聴けば聴くほど心に染み入ります。荒々しくて青臭い初期の2枚もあれはあれで好きだけど、10年後にどっちを聴いてるかといえば、きっと『ユグラシル』のほうだろうなあ。 |
 |
BURNSIDE PROJECT 『THE NETWORKS, THE CIRCUITS, THE STREAMS, THE HARMONIES』 |
ニューヨークのイースト・ヴィレッジにある有名なレコード屋「OTHER
MUSIC」の店員であるジェラルド・ミハルが率いるバーンサイド・プロジェクトのデビュー作。世界中のいろんな民族音楽からスーパーカーやボアダムスなどの日本の音楽まで幅広く音楽を愛するカナダ人の友達に薦められた作品なんだけど、とっても素敵です。 さすがニューヨークの有名レコード屋の店員って感じでロック、ギターポップ、ヒップホップ、シューゲイザー、ニューウェーブ、ポップス、フォーク、テクノ、ドラムンベース、エレクトロニカ、ポストロック・・・いろんな音楽がいい感じに同居した良質のポップ・ミュージックに仕上がっています。エレクトロニカ以降の多様なビートにダイナミックなバンド演奏やオーガニックなアコースティック楽器が複雑ながらも美しく絡み合い、その上を男女ボーカルの美しく甘いハーモニーが浮遊。次々と多様な音楽性と予想を裏切る転調、そしてグッドメロディーが繰り出されるところなんかは僕の大好きな日本のバンド、BOaTを思わせたり。サウンド的にはちょっと違うけどね。サウンド的にはスーパーカーにちょっと近いかも。フューチャラマの路線のまま進化したら、こうなってそう。 とりあえずスーパーカーとかポスタル・サービスを好きな人は気に入るんじゃないかな。それ以外の人にも多くの人に聴いてもらいたい傑作。特にロックを中心に幅広く音楽を聴く人にはお薦めです。 |
 |
BUSH OF GHOSTS |
デタミネーションズの市原大資氏が率いる大阪のスペーシーなダブバンド。 ダブを基調としてアフロ、ラテン、レゲエなど異国感溢れるサウンドです。クールでダンサブルなトラックに突然、乗っかってくる一癖も二癖もある日本語のボーカルがオリジナリティを生んでいます。 その独特のボーカルや宇宙をバックにカンフーしてるジャケットなど全体的にダサかっこ良さが漂っています。大阪らしいバンド。ダサイとカッコイイのギリギリの線をいってるので好き嫌い分かれるかもしれないけど個人的には傑作。 |
 |
BUSH OF GHOSTS 『ELECTROPICA』 |
DETERMINATIONSのトランペット奏者、市原大資と同じくキーボード奏者のYOSSYを中心とした近未来ダブ・レゲエ・バンド、BUSH
OF GHOSTSの2ndアルバム。 レゲエ、ダブ、アフロ、ラテンなどを基調に、現代的なアレンジ、エフェクトなどを施したダンサブルなトラックに、怪しさ満天ドロドロの個性的なボーカルが絡む。ジャマイカ、大阪、宇宙を行き来する。ジャマイカから遠く離れた大阪だからこそ生まれた全く新しいダンスホール・レゲエ。本場ジャマイカ人じゃなくて、日本人がやるからこその妙なインチキっぽさがあって、それがプラスの方向に作用しています。とにかくユニーク。そして、ユニークなだけで終わらず、しっかりカッコいい。これはクセになります。 ちなみにジャケットはEGO-WRAPPIN'でお馴染みの小澄源太が担当。これまた、いい感じです。 |
 |
BUTTER08 |
チボ・マットの2人とジョン・スペンサー・ブルース・エクスプロージョンのラッセル・シミンズによるユニット。 |
0/A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P/Q/R/S/T/U/V/W/X/Y/Z/更新履歴
あ/か/さ/た/な/は/ま/や/ら/わ/O.S.T./V.A./特集/MUSIC・BBS/MUSIC MENU/TOP